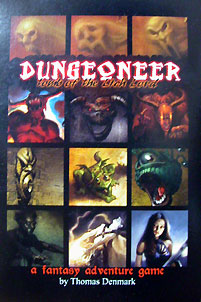ホームページを見て回っている時に、面白そうな新作…という書き込みをたまたま目にしました。それから数日後、仕事帰りに立ち寄った書店の片隅にひっそりと置かれているのを偶然発見し、思わず買ってしまったゲームです。Copyrightは2002年となっていますが、今年(2003年)の2月中旬にカリフォルニア(米国)で開催されたDunDraConというゲームのコンベンションでお披露目となり、人気を博した(らしい)ゲームです。
パッケージ絵は、右の写真の通りで、ややおどろおどろしい雰囲気を醸し出しています。意外とコンパクトなパッケージで、中には120枚ほどのフルカラーのカードと説明書が入っているだけです(ゲームを始めるには、最低限、6面ダイス2つを準備する必要があります)。
中に入っているカードのうち3枚は、コンポーネント用となっていて、はさみで切り取れば、そのままキャラクターの駒や、危険ポイントなどをしめす駒となります。もちろん切り取ってもいいのですが、説明書にも書かれているように、できればキャラクターには適当なフィギュアを用意した方が雰囲気が出ます。さらに生命(Life)の残りポイントを示すのには、(メモ用紙に鉛筆書きする代わりに)6面ダイスがお薦め。他の道具もガラス玉などで自分なりにアレンジするのをお薦めします。 |
|
 |
このゲームは、危険なダンジョンの中を探索し、与えられた3つのクエストをこなすゲームです。各プレイヤーは、戦士・魔法使いなど異なる能力を持つ4人のヒーローのうちの一人となり、クエストの達成を目指します。最初に3つのクエストをやり遂げるか、あるいは、最後までダンジョンの中で生き延びたヒーローが、このゲームの勝利者となります。
このゲームで使用するカードの種類は4つ。ヒーローカード、クエストカード、マップカード、アドベンチャーカード。うちクエストカードは14枚あり、中に書かれているクエストは全て異なっています。マップカードは探索するダンジョンそのもので、落とし穴などがある通路のタイプと、何らかの効果を持つ部屋のタイプがあります。部屋のドアには鍵がかかっていたり、罠がしかけられていたりします。もちろん素通りできるドアもありますが。またアドベンチャーカードには、宝物(装備品など)、恩恵(体力回復など)、不幸(トレジャーカード1枚捨てるなど)、遭遇(モンスター、罠など)の4つの種類があります。 |
ゲームの準備としては、まずヒーローカードを一枚ずつひいて、各プレイヤーの使用するキャラクタを決定。次に一人3枚ずつクエストカードをひき、各自クエストを決定。最後に手札として、5枚ずつアドベンチャーカードをひきます。アドベンチャーカード以外は表向きにして、前に並べておきます。マップカードの入り口の部屋を、プレイする場所の中央に置き、そこに各プレイヤーのキャラクタ駒を配置。さて、ゲームスタートです。
手番にやることは次の5つ。(1)カードを1枚捨てる。(2)手札が5枚になるようにアドベンチャーカードを引く。(3)他の人に対して、罠カードやモンスターカード、不幸カードを出す。(4)マップカードの山から1枚引き、ダンジョンを生成する。(5)キャラクタを動かす。そして次のプレイヤーに手番が移ります。留意点としては、各プレイヤーの手番の最初には、マップの効果がリセットされます。例えば、鍵のかかったドアを一度開けていたとしても、手番の最初には再び鍵がかかっている状態になるのです。またダンジョンの生成で、マップカードは絵がつながるようにしか配置することができません。
|
 |
 |
プレイするたびにマップが変わるので毎回違ったダンジョンで楽しむ(苦しむ?)ことができます。またこのゲームの大きな特徴として、Peril(危険)、Glory(名誉)の二つのポイントがあります。マップカード(左の写真参照)の上に赤い字で書かれている値がPeril(以下、危険ポイントとよぶことにします)、そして緑の字で書かれている値がGlory(以下、名誉ポイント)。それぞれ自分の手番にキャラクタを移動するたびに、その部屋にかかれた危険ポイント、名誉ポイントの二つのポイントがたまります。名誉ポイントをため、そのポイントを使って、手札のアドベンチャーカードの中から宝物カード(装備品など)を出せるようになります。逆に、危険ポイントはたまるとたまるほど危険な状態になります。何故なら、その自分にたまった危険ポイントが、他プレイヤーがあなたにモンスターなどを呼び出すコストとして使われるからです。危険ポイントを抑えれば、他プレイヤーから、強力なモンスターを出されることも減るでしょう。 |
クエストについても一言触れておきましょう。指定の部屋に行ってモンスターを倒すクエスト、ある部屋に隠れた暗殺者を探し出し倒すクエスト、特定の部屋にいる老魔法使いを図書館までエスコートする(連れて行く)クエストなど多種多様なクエストがあります。エスコートしている間は、移動力が1下がる、戦闘力が1下がるなどの条件が与えられる場合もあります。マップ次第では、大変な労力を費やすクエストもありますが、手番の行動の「カードを1枚捨てる」時に、クエストカードを捨てることもできます。その場合には、入り口の部屋まで戻り、名誉ポイントを2つ使うことにより新たなクエストを受けることができます。クエストをクリアするたびに自分のレベルが一つあがり、戦闘能力、移動能力などが上昇します。
装備品が調い、レベルもあがってくると、ダンジョン探索も少しずつやり易くなり、キャラの成長を感じることができます。しかし特に最初のうちは、キャラの能力も低く弱いので、慎重に行動することが必要です。この辺、アメリカのコンピュータRPGをプレイしているような感覚です。
|
 |
 |
このゲーム、まだまだ言い足りない色々な要素が多数ありますが、ルール自体はわかりやすく、すぐにプレイできます。米国では、CCG(Customizable
Card Game、Collectable Card Game)とボードゲームの要素を合わせ持った傑作などと言う人もいるようです。ただ一つ残念な点をあげるとすると、説明書の出来がいまひとつなところでしょうか。A4大のサイズの用紙の裏表に写真・絵を含めてぎっしり説明が書いてあります。それ自体はわかりやすいのですが、実際プレイしてみると、ちょっとルールが不足している感じがあり、(例も少ないので)ルールの解釈に戸惑うことがあります。また誤植もあったりして、さらに混乱します。そういう点が非常に残念です。ただ幸いなことに、このゲームにはテストプレイの頃からのメーリングリスト(ML)があり、そこで、FAQやマニュアルの訂正などがまとめられているので、そこを読めばほぼ疑問は解消されます。制作者自らが積極的に問い合わせに回答されています。またゲームに便利な補助シート、駒などのデータファイルも登録されているので、プレイされる方はMLへの加入をお薦めします。 |
さらにこのゲームには、今後拡張カードセットの発売予定もあり、第一弾として今年7月に発売が決まっています(もうほぼ完成しているそうです)。というわけで、私も心待ちな状態です。
最後に、このゲームの魅力をあげるとすると、カードだけというシンプルさにもかかわらず、色々な楽しい遊びの要素がぎっしり詰まっている点、それにカードデザインが一枚一枚美しく魅力的な点、そして単純なカードバトルにとどまらず、クエストという要素が中心に置かれている点でしょうか。
このゲーム、2人でも結構楽しめますが、3人くらいが一番いい感じです。4人だと時間がかかりすぎるかも知れません。コンパクトで持ち歩き可能、しかし、中身はボードゲーム並の濃さなので(カードの裏にはファンタジーボードゲームと書いてあります)、どこででも本格的なゲームを楽しみたい人に特にお薦め。私の最近お気に入りのカードゲームです。
(2003年4月10日・記)
データ
Thomas Denmark作
(c)2002 Citizen Games/2−4人用/
10歳以上/15−20分(1人あたり) |
 |